



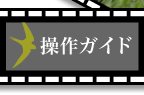
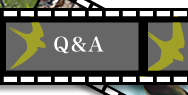

ハイビジョンカメラの小型化やビデスコ機器の進化、Retina ディスプレイ搭載 iPhone / iPad の登場により、映像を「記録する」「見る」の両環境は大きく変わっています。野鳥の表情やしぐさ、体の細かな質感までリアルに感じられる映像を、手軽に楽しむことができる時代になりました。
画面をタッチするだけで、いきいきとした野鳥に出会うことができる。こんな鳥見 Smart Birding はいかがでしょうか。
同じ映像を何度かリプレイしてみると、野鳥の視線やその時の周囲の状況など、一度では気づかなかったことが見えてくることがあります。スローやコマ送りで速い動きを分解して見てみると、肉眼ではわからなかった野鳥の一瞬の表情や、優れた身体能力を再認識させられます。
また、家族や仲間と一緒に見るのも楽しい時間です。おもしろい表情や興味深い行動など、新たな発見や「なぜ?」が生まれることもあるでしょう。
ひとつの映像をいろいろな見方をすることでじっくり味わおう。これが一つ目のコンセプトです。
野鳥の自然な行動(=生態)を映像で記録をしておくことはとても重要なことだと考えています。Smart Birdingの映像は、できるだけストーリーをつけずに行動や季節や個体のバリエーションを多く収録し、ユーザーが見たいシーンを好きな順に見れるよう、観察ポイントを設けました。
再生中、気になるシーンはワンタッチで止めて画面を拡大して見たり、コマ送りで少しずつ戻して見たり、スロー再生でもう一度見たり。自分のペース何度でも。ユーザが直感的に操作しやすいような機能とユーザーインターフェイスを心がけました。
大好きな野鳥たちを何も考えずにぼーっと見ていたいというときもありますよね。そんなときには、好きな音楽をバックにランダム再生する機能なども用意しています。
葉の茂った森ですばしっこい野鳥の姿を捕らえるのはなかなか難しいものですね。やっと双眼鏡におさめてピントが合った瞬間に飛んでしまったり・・・。湖や海では、距離が遠くてぼやけたり、陽炎や霧に阻まれたり・・・。テレビや映画で見る映像作品のようにはなかなかいかないですね。
Smart Birding では、きれいな映像だけを抽出・編集するのではなく、実際の鳥見に近い状況を活かして、編集しすぎないようにしています。野外で超望遠のビデオ撮影となると、手振れや雑音などは避けられません。しかし、美しいきれいな作品をめざして、生態の記録としては貴重な瞬間をカットしてしまうのは、あまりにも心苦しいのです。撮影の自然な流れを重視し、少々暗かったり雑音が混じったりブレたりしても、記録として残しておくことに意味があると判断したものは極力そのまま収録しています。
演出的な効果もほとんど施していません。野鳥のそのままの美しさとスピードを体感していただければと考えています。編集ソフトで速度を変更した箇所については観察ポイントに(slow)と表示しています。
実際のフィールドでは、枝に隠れて姿が見えにくかったり、ピントが前後したり、こういうふうに見えるのか、というところを体感しご理解をいただければ幸いです。
野鳥写真家と言われる人も増え、野鳥写真を撮る一般カメラマンも増えました。撮影機材の高度化もあいまって、写真や映像の質は日々向上しています。テレビの自然番組でも、すごい映像や貴重な映像を見る機会も増えてきました。一人の野鳥好きなものとしてこうした機会が増えることはうれしい反面、良い写真や映像を撮ろうとするエネルギーが、野生動物や自然環境に悪い影響を与えてしまう可能性も否定できません。
野生動物の撮影方法の是非は簡単に結論を出せることではありません。ただ、わたしたちが大切にしていること、忘れないようにしていること。それは野鳥が主役であること。決して、写真や映像という「作品」でも「カメラマン」でもないということです。
撮影を手がけてくれた鈴木良二氏は熱くなりすぎることなく地道な努力を続けてフィールドに立ち続けてくれました。「鳥が出てきてくれた」「撮らせてくれた」、彼から撮影の話しを聞くときによく出てくる言葉です。一度だけ撮影に同行させていだいたとき、彼は個や我を消して自然と現場の空気のようになっていました。レンズの向こうにいる主役の鳥と繊細に謙虚に向かい合っていました。
多くのカメラマンがこんな気持ちや感覚を理解してくれたらと願わずにはいられません。